どうも、Akaneです。
高知に移住してきて初めて知った植物の一つが、この四方竹。
「しほうちく」と読みます。
珍しく秋に食べられるタケノコ!!
今回は、そんな四方竹の謎に迫ると見せかけて、食べ方とかをレポートします。笑
四方竹とは
ほぼ高知県が生産を独占している模様。
明治時代に中国から持ち込まれたそうな。
この竹、何と言っても面白いのはその形!!
名前の通り、四角形なんです。丸くないんです!
太さはというと、孟宗竹や真竹は建築材の柱に使えるほど太いですが、四方竹は細いです。
なので、当然タケノコも細いです。
孟宗竹や真竹など、基本的にどの竹も春に出てくるのに、四方竹は秋。
秋にタケノコが食べられるなんて、幸せ過ぎる!!
四方竹の食べ方
収穫
というわけで、まずは収穫から。
高知県の南国市が四方竹の主な生息地。
しかし、私たちが住む嶺北地域でも、ちょこちょこと栽培されている方がいます。
我々は幸運にも、収穫させてもらえる機会を得ました。
まず、タケノコの先端部50cmくらいを鎌で切り取ります。
以上です。笑
アク抜き
さて、収穫が済んだらすぐに下処理をした方が良いらしいです。
我々は下記の手順で実施しました。
- 先端5cm〜15cmを切り落とす。
→先端付近は身が無いのと、長過ぎると鍋に入り切らないのが理由で、この作業をしました。必須ではありません。 - 鍋に入る大きさに切って、たっぷりの水から茹でる。沸騰したら弱火。
→水に皮の色が付くまで茹でる。我が家では、1時間半位でした。
→全体が水に浸るよう、落し蓋的なものがあればベター。

- 水に浸して、皮を剥く。そして、1日位水に浸し続ける。
→時々水を入れ替える。

- かじってみて、渋かったらもう1日水に浸す。笑
以上で下処理完了!
調理例(天ぷら、土佐煮)
四方竹の天ぷら
- 小麦粉、水、塩少々を混ぜる。
- 四方竹を投入。
- 油であげる。
以上で完成!!!!
しかし、根元の方は固くあまり天ぷらには向いていないかも。。穂先は柔らかくて美味しいです!
四方竹の土佐煮
- 水、醤油、みりん、酒を入れ、沸騰させる。
- 食べやすく切った四方竹とキノコを投入。5分ほど煮る。
- 鰹節を加えて、さらに5分ほど煮詰める。
以上で完成!!!!
これは大成功!!家族にも好評でした!
しかし、一部の四方竹の根元の方はすでに竹っぽくて、繊維だらけでした。。
栽培
お待たせしました。どうも、Yutaです。笑
最近、野菜を食べても果物を食べても、種を栽培用に保存しています。
そんな私ですから、この四方竹、育てないワケがない!!笑
今回、収穫の際に地下茎も丸ごと採取させてもらったので、それを『はじまりの家』に移植してみました。
竹の栽培の注意点
これは超重要ポイントです。
竹は放置しておくとそこら中に繁茂して、大変な事になるイメージがあると思います。
実際、タケノコが床下を突き破って出てきたなんて話もあります。
しかし、竹には2つの種類があるのです!
それは、この2つ。
地下茎タイプ・・・地下30cmあたりに地下茎を伸ばし、広範囲に繁殖。
株立ち・・・1つの株から複数の茎が立つ。
もうお分かりの通り、株立ちタイプなら、庭に植えても心配ご無用。
しかしながら、残念な事に四方竹は地下茎タイプ。
細心の注意が必要です。
移植場所の整備
前述の通り、下手をするとそこら中に拡がってしまう竹。
なので、地下茎が拡がらないよう、事前に移植場所に細工をしておきます。
まず、栽培スペースの周囲に、深さ50cmの溝を掘ります。
竹の地下茎は、池や川など水が溜まっている場所には侵入してこないという話を聞いた事があります。
『はじまりの家』のこの場所は、湧き水が出るポイントなので、50cm掘ればおそらくちょっとした小川みたいになります。
なので、これで終了!!
心配なら、溝にトタン板やブロックを入れて物理的に地下茎が出られないようにするのも有効な策です。
移植
まぁこれは、穴を掘って採取した地下茎を植えるだけ。
移植したら、一度水やりをしましょう。
今後、これが根付いてくれるのかは乞うご期待!
定期的にこの記事に経過報告を付け足していきます!
ちなみに、上記の移植は、2018/10/28です。
苗は、買うこともできるみたいです。笑
【ラッキーシール対応】花木 庭木の苗/シホウチク(四方竹)6号ポット
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました!!!
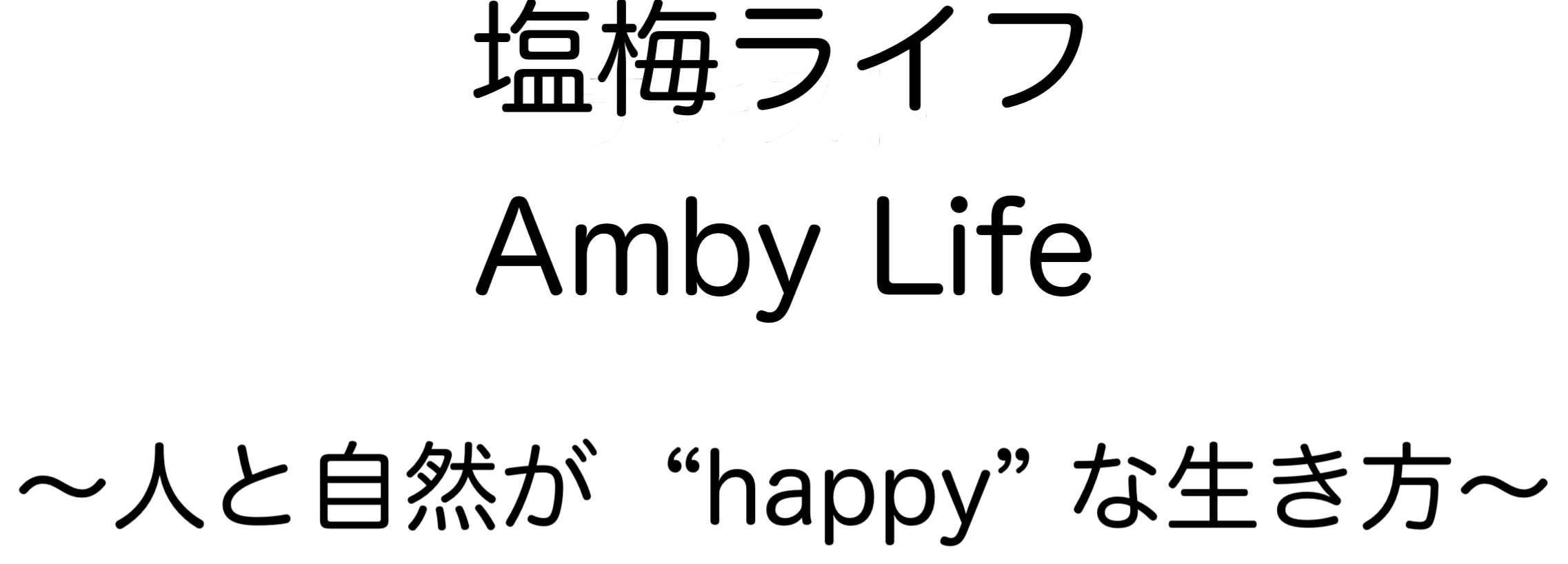














コメント